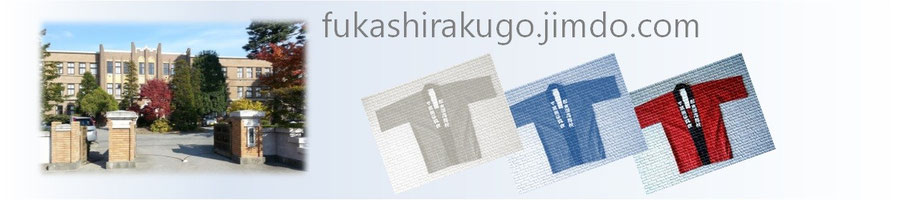はじめに
明烏、三枚起請、居残り佐平次、付き馬、錦の袈裟、富久、品川心中・・・
江戸時代、庶民の最大の楽しみといえば、一生に一度は行きたい「お伊勢参り」と、そして色里「吉原」。
現代とは違い、吉原は単なる歓楽街ではなく、江戸の文化と流行の発信地でもありました。
また、華やかで艶やかなその裏で、「苦海」といわれる悲惨な遊女達の暮らしがあったことも事実です。
遊郭で織り成された男女の喜劇と悲劇が、「郭話」となって落語の世界にも数多く存在しています。
色里を知ることは、すなわち江戸の文化を知ることにもつながるかもしれません。
そんなわけで、このコーナーでは色里・吉原を中心として、江戸の遊郭の歴史としきたりについて紹介してみたいと思います。
※主に「江戸三〇〇年 吉原のしきたり」渡辺憲司監修を参考にしています。

1.吉原の誕生
慶長10年(1605年)、江戸柳町で遊女屋を営んでいる庄司甚右衛門をはじめとする遊女屋稼業の者たちから遊郭設置願いが幕府に出された。江戸に散在する遊女屋を一ヶ所にまとめ営業したいというのである。
しかし、この時の甚右衛門たちの願いは、時期尚早という理由で却下された。
諦めない甚右衛門たちは、慶長17年(1612年)同様の願いを提出し、今度は幕府も願いを取り上げた。実際に営業が許可されたのは5年後の元和3年のことであった。
このときの遊郭設置条件は、
一.設置場所以外では遊女屋はいっさい認めない。
一.客は一昼夜以上店にいてはならない。
一.遊女は贅沢な着衣は用いないこと。
一.遊郭は質素なたたずまいとし、町役は他の江戸の町と同様にすること。
一.身元不審の者は奉行所へ通報すること。
の五箇条だった。
幕府は設置場所として、日本橋葺屋町の北はずれにある二町四方の湿地帯を与えた。この湿地帯にはどこもかしこも葭が生えており、このままでは建物は建てられないほど地盤は軟弱であった。
甚右衛門たちは早速地盤整地のための埋め立てを開始する。この工事は一年ほどかかり、どうにか元和4年(1618年)11月、置屋17軒、揚屋24軒で営業が始まった。
この頃には「遊郭」という言葉はなく、単に「遊女町」「傾城町」と呼ばれていた。遊女を傾城と呼ぶのは、君主が色香に迷って城が傾いたという中国の故事から来ている(「漢書・外戚伝」の逸話より)。
埋め立て後、そこら辺一帯が葭の原だったことから、新たに「葭原(よしわら)」と名付けられた(アシは悪しに通するのでヨシとも発音した)。そして、さらに商売繁盛の縁起をかつぎ「吉原」となった。ここにいずれ日本最大の歓楽街へと変貌する吉原が誕生したのである。
2.新吉原の誕生
吉原の誕生した元和4年は豊臣氏滅亡の4年後で、新しい日本の中心都市・江戸へと人々は集中し始めていた。
また、寛永16年(1635年)に発令された「武家諸法度」による参勤交代制度などにより、江戸の人口は膨張を加速していった。これらの人口を構成していたのはほとんどが男であり、必然的に吉原の商売は潤いをみせたのである。
誕生当初の吉原は町人地から離れた辺鄙な場所だったのだが、江戸の人口が増加するにつれて周囲には町人が住みだし、次第に商業地、町人地の中心になってしまったのである。
このため、幕府は吉原をさらに江戸の郊外へと移転させる計画を立てた。吉原のような悪所が江戸の顔のように繁栄しているのを快く思わなかったのである。それには、この頃の客の中心が武士だったこともある。
明暦2年(1656年)10月、幕府から吉原に移転命令が下った。移転先は、浅草・浅草寺北の郊外にある日本堤という場所で、通称浅草田圃といわれたところである。
郊外の人気のないところへの移転命令に対し、当然の如く吉原の遊女屋連中は反対した。これに対し、幕府側も心得たもので、この移転に対して破格の条件を出した。その条件とは、
一.土地面積は今までの1.5倍与える(約2万坪)。
一.移転料を1万5千両支給する。
一.今まで昼間だけだった営業を夜も認める。
一.江戸中の風呂屋にいる湯女と称する遊女の営業を一切禁止する。
一.郊外へ移転するので町役である火消し作業を免除する。
という、かなり優遇されたものだった。
明暦3年8月浅草田圃への吉原の移転が完了した。最初にできた吉原を「元吉原」、移転先の吉原を「新吉原」として区別するが、一般に「吉原」といった場合、新吉原をさしている。
新吉原は以後300年、昭和33年(1958年)4月に施行された「売春禁止法」まで続き、地名は変わったものの現在も独自の風俗地区として存在している。
ちなみに、「東京都台東区千束」というのが現在の地名である。
新吉原完成から数ヶ月後、幕府は江戸中の風呂屋へ通達を出した。一切の遊女(湯女)をおいてはいけないというものである。職を失った湯女たち約600人全員が吉原送りとなった。幕府は移転に際する約束を守ったのである。
こうして、規模が1.5倍になった吉原は遊女の数も元吉原時代の2倍になり、2,000人近くを数えた。吉原の案内書である「吉原細見」によれば、享保13年(1728年)の遊女の数は2,552人とあり、弘化3年(1846年)には7,197人とある。遊女の数は増え続けていったのである。
さらには、吉原の移転に伴い客層にも変化がでた。元吉原時代は昼間のみの営業だったため、暇な武士階級が客の中心だったが、夜の営業が許可されたことにより、客層の主体が町人になっていったのである。
「世の中は暮れて郭は昼になり」と川柳にあるとおり、吉原は江戸期を通して不夜城となったのである。
3.吉原の仕組み
(1)吉原の概略
吉原で遊ぼうという客は、浅草方面から日本堤を通り、吉原の入り口である「五十間道」から大門へと向かう。五十間道は日本堤から大門の中が見えないように「くの字」に折れ曲がっている。道の両側には茶屋が並んでおり、ここで吉原の案内などを行っていた。
大門を入るとすぐ右手に「四郎兵衛会所」という番所があった。郭内の秩序を維持する吉原独自の警察だが、実際には遊女の脱走監視が主な役割だった。向かい側には町奉行所から派遣されてきた岡っ引きが詰める番所もあった。
左右の番所をはさんで大通りが真っ直ぐに延びており、これが「仲之町」である。
イメージを掴んでいただくため、概略を[十七世紀後期の吉原の略図]に示す。
「どうだい八つぁん、今夜は景気づけにわぁっと、『仲』へでも繰りだそうじゃねえか」
というように、落語の中でも吉原を表す通称として「仲」という言葉がよく出てくるが、これはこの仲之町から来ている。
仲之町をはさんだ両側には引手茶屋が軒を連ねている。この茶屋は値段や遊女の取り決めをするところで、交渉が成立すれば登楼ということになる。
二階に通されて客はそこで遊女が来るのを待つ。部屋待ちの遊女は茶屋から呼び出しを受けると客に会いに行く。花魁が来るとそこで酒席が開かれ、宴が終われば一緒に花魁の部屋(見世)へ行く。
二階に通されて客はそこで遊女が来るのを待つ。部屋待ちの遊女は茶屋から呼び出しを受けると客に会いに行く。花魁が来るとそこで酒席が開かれ、宴が終われば一緒に花魁の部屋(見世)へ行く。
ただし、引手茶屋を利用するのは金に余裕のある上級の客がやることで、ほとんどの客は大通りから横町に入り、手頃な遊女を選ぶ。横町には「張見世」と呼ばれる格子のある店が並んでおり、客は外から遊女を選び、中に入るのである。
さらに銭のない客は、おはぐろどぶ沿いにある二つの河岸に行く。「浄念河岸」と「羅生門河岸」である。ここに並んでいるのは、吉原でも最も安い遊女のいる見世である。これらの見世は時間を区切って銭で遊ぶことが出来たので「切見世」あるいは「銭見世」とも呼ばれた。
大門が開くのは卯の刻(午後6時)で、閉まるのは亥の刻(午後10時)である。張見世は正午から午後2時頃まで営業し、午後4時で一旦閉める。日没後再び見世を開き、大門が閉まった後も午前0時頃まで営業していた。午前2時「大引け」の拍子木が打ち鳴らされ、賑わっていた吉原もこれを境に静
まるのである。
まるのである。
(2)見世のランク
見世のランクは置いている遊女の値段や評判で決まった。
最上級クラスの見世は「大見世」といい、浮世絵に描かれるような高級な花魁がいた。次が「中見世」と呼ばれるクラスで、規模も遊女の質も大見世より一段落ちる。
さらに、一分女郎(料金が昼一分、夜一分の遊女)だけがいる見世を「大町小見世」、二朱女郎(料金が昼二朱、夜二朱の遊女)が中心の見世を「小見世」と呼んだ。
この他に、前述の「切見世(銭見世)」がある。
(3)遊女のランク
初期の吉原(元吉原)時代、遊女は「太夫」「格子」「端」の三ランクに分かれていた。
太夫と呼ばれるには、姿形が美しく、かつ教養も備えていなくてはならなかった。歌舞音曲はもちろんのこと、和歌朗詠、囲碁、茶道、華道に通じており、たとえ大名クラスの客の前に出ても恥ずかしくないだけの品性や才知もあったのである。
その下の格子というランクは、文字通り格子のある見世に並び「格子女郎」と呼ばれた。この時期、太夫・格子までを一般に「花魁」と呼んだ。
端は小見世以下の遊女たちの総称である。江戸市中で取り締まられ吉原送りになった湯女や遊女が増えてくると、端女郎は、「局」「端」「切見世」に細分化され、元吉原末期には都合五ランクに分かれた。
新吉原になって遊女の数は増えたものの、およそ70名ほどいた太夫が半数以下に減ってしまった。最大の顧客層であった地方の大名の出入りが、幕府の「金減らし」政策等により減ってしまったことが大きな要因となっている。
太夫は吉原の看板であるため、みっともない格好はできなかった。前述の通り教養も必要であり、専属の使用人も雇わねばならず、とにかく金がかかる。いい金主がついていなくては、なかなか維持はできなかったのである。
太夫の数はその後もどんどん減っていき、宝暦二年(1752年)ついに一人になり、その太夫も8年後に引退したため、吉原から太夫が消えた。以降、「花魁」という呼び名からは上級の遊女を示す意味合いが薄れていき、幕末には単に遊女全体をさす呼び名になる。
その他の遊女たちの名称も時代とともに変化していった。以下に遊女のランクと名称の変遷を示す。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(4)吉原で働く人々
遊女という「女」が主役の吉原でも、それを支えているのは「男」たちである。経営者である楼主の下に、様々な役割を持った男たちがいた。
男たちは一般的に「若い者」あるいは「若い衆(し)」と呼ばれていた。歳をとっても若い者である。彼らは見世の裏方で、楼主に一切を任された番頭の命令で動き回る。
【妓夫】
「ぎう」とも「牛太郎」とも呼ばれる、客の呼び込み役である。見世の入り口に「ぎう台」という番台のようなものが設けられ、そこに座って客を呼び込んだ。
彼ら牛太郎には、金が足りない客についていって集金する役目もあった。この役目を「付き馬」(付け馬)あるいは単に「馬」といった。
『夕べ格子で 勧めた牛が 今朝はのこのこ 馬となる』
落語の「付き馬」のまくらにも出てくるお馴染みの都々逸である。牛が馬になるといって江戸っ子は喜んだ。
「ぎう(牛)」については、「鼻で回る=祝儀(ハナ)で働き回る」の洒落から来たという説もあり、さらには、中国の花街で牛車に乗ってくる遊客を引き付けるため、牛の好物の塩を店頭に置いたという、盛り塩からの起源という説もある。
【見世番】
見世の中にいて見世内の雑用を行う。呼び出しがかかった遊女の道中に付き添い、提灯や傘を持つ役目もあった。
【二階番】
妓楼の二階を整理整頓する役目である。二階に詰めていて、各部屋から呼ばれたりした場合、その部屋に行き用件を聞くなどという雑用もする。
【不寝番】
火の用心など、夜中の見回りのほか、もめ事の仲裁などをする・
【料理番】
見世の一階の奥にある厨房で客や従業員の食事を担当する。
【風呂番】
風呂を沸かしたり掃除をする役目である。
【二階廻】
夜、二階の各部屋を廻って行灯の油を足していく役目。「油差し」とも呼ばれる。部屋に入るときはいきなり入るので、客からは嫌がられた。
【掛廻】
見世のツケの集金をする役目である。ただし、ツケは誰でもきくというものではなく、常連や名の知れた商家、武家に限られた。
【物書】
番頭の側に座っていて、客の名前を書いたり、証文を作ったりする役目で、商家なら手代のような仕事をする。
【中郎】
見世の雑役夫である。見世前の掃除、一階の掃除、ゴミの廃棄など、一切の雑役を担当する。
以上が見世の男たち(若い者)に与えられた仕事だが、他にも女に与えられた「遣手」という役目があった。
【遣手】
客は遊女を決めて見世に上がると、二階の引付部屋に通される。ここで登場するのが遣手である。遣手は元遊女。だいたい30歳くらいを過ぎた、当時でいう大年増なので「遣手婆」ともいわれる。
引付で客は遣手と交渉する。遊女の値段から、酒や食べ物、芸者衆を呼ぶかどうか、何時までいるつもりなのかなどをやり取りする。マケたり、ときにはふっかけたり、見世を儲けさせるために上手に値段を交渉する。
客が指名した遊女ではなく、違う遊女を勧めることもある。あまり客のつかない遊女をうまく回すのである。したがって遣手は遊女を含めて遊郭のすべてに通じていなければならない。基本的な遊女の値段は決まっているものの、その他のお金は遣手の胸先三寸でどうにでもなった。
遣手は吉原の主人公ではないものの、経営者から見れば重要な任務を帯びた役目であり、見世の繁盛は遣手次第という面もあったのである。
4.吉原の遊び方
切見世のような下級の見世を除き、吉原では遊女との「疑似夫婦関係」を結ぶ必要があった。粋を気取る江戸っ子は吉原なりの情緒を求めており、惚れて通うことを楽しみにしていたのである。
客として吉原で遊ぶとき、吉原の決まり事を理解していないと無粋な客として蔑まれてしまう。ひどいときには、遊女をはじめ茶屋や見世の者たちからも無視され、見世にも入れてもらえないこともあった。
【初会】
吉原初体験のとき、客は細見(吉原のガイドブック)を見たり、五十間道に並ぶ編笠茶屋で情報を仕入れ、目星を付けた引手茶屋や遊女屋に登楼する。
昼三や附廻以上の遊女の場合は、最初に引手茶屋に行き、茶屋の案内で遊女屋へ向かうことになる。そして遊女屋の二階の引付部屋に宴席を設け、芸者を呼んだりして遊女が現れるのを待つ。
それ以下の遊女なら、直接見世に行き、酒や台の物を頼んで引付部屋で指名した遊女を待つことが多い。さらに下になると、料金を遣手に渡すと遊女
が現れ、すぐに部屋に通される。そこに簡単な台の物が運ばれてくる。
が現れ、すぐに部屋に通される。そこに簡単な台の物が運ばれてくる。
遊女がやってくると、遊女は上座、客は下座に座り、酒や台の物を前に簡単な宴席になる。酒は客の方が遊女に勧めるが、遊女は一言も発せずにこれを断る。中には芸者を呼んで盛り上げようとする客もあるが、堅い雰囲気の中で初会は終わる。
初会とは、いわば見合いのようなもので、互いの視線は合わせても、会話はなくあくまでも形式的にコトが進むのである。それでも料金は規定通り支払われる。
『初会には 壁へ吸いつく ほど座り』
【裏】
二回目に同じ遊女に会うことを「裏」といった。これを「裏を返す」ともいう。「裏を返さないのは江戸っ子の恥」といわれるように、一度遊女に会ったら次も同じ遊女に会うというのが江戸っ子の矜持だった。
なぜ裏というのかというと、遊女屋には遊女の名札が下がっている。客が付くとその札を裏返しにして、仕事中ということが分かる仕組みになっている。
この札を、客が指名して裏返すことから、裏ということになった。京や大坂では「裏壁返さぬは男の恥」といって、左官の壁塗りから出た言い方ともいわれている。
この札を、客が指名して裏返すことから、裏ということになった。京や大坂では「裏壁返さぬは男の恥」といって、左官の壁塗りから出た言い方ともいわれている。
吉原の決まりでは、一度会った遊女を代えることはできない。違う見世に行ってもいけない。一つの見世の遊女に決めたら、最後まで筋を通すことを求められるのである。初めてのような顔をして別の見世に行き、違う遊女を頼んでも、ばれたら法外な罰金を取られたり、吉原への出入りができなくなった
りする。
りする。
どうしても女を代えたいときは、それなりの金品を見世と遊女に支払って了解を得なければならない。このあたりの独特の決まりが、単なる女遊びと違う吉原独自の男女関係、つまり疑似夫婦関係を醸成していた。
裏を返したからといっても、初会よりは打ち解けるが、まだまだ男と女の関係にはなれない。初会に引手茶屋で遊女を呼んだ場合は同じ茶屋へ行き、同じように呼び出してもらう。そして、同じように宴席となる。
ただし今度は、少しばかりの酒のやり取りと会話程度のお付き合いがある。名前はまだ呼んでくれない。ただ、「客人、客人」と呼ぶだけなのだ。見世で直接指名した場合も、引手茶屋で前回と同じことが繰り返される。料金も同じである。
酒にも台の物にも手を付けず、ひと言も口を聞いてくれなかった初会よりは少しだけ前進する。
『枇杷ひとつ 食ったが裏の しるしなり』
【馴染み】
三回目に通うと馴染みの客と呼ばれ、それまでと打って変わって、遊女が打ち解けてくる。いわば、見合いをし、結納をして、やっと結婚に漕ぎ着けたというわけである。
この間柄になると、初めて遊女の部屋に通され、宴席となる。引手茶屋からその遊女の見世にある部屋まで案内されるのである。そして名前で呼ばれるようになり、見世の方でも客専用の箸を用意する。さらに客の紋所が入った箸包みの紙が作られて、箸をそれに入れて遊女が預かる。定紋付きの箸
箱を作ることもあった。
箱を作ることもあった。
客の方も料金だけで手ぶらというわけにはいかない。馴染み金という祝儀を出さなければならないのである。これを「馴染みをつける」という。遊女には別に「床花」という祝儀も出す。その額は客の気持ちに任されてはいたが、一般的には五両から十両といわれている。
こうしてようやく、遊女と枕をかわすことになるのである。
馴染みになった客が帰るとき、遊女は大門まで送った。初会や裏では、店先までしか送らないが、疑似夫婦関係ができあがると扱いが変わるのである。
5.吉原への道
徒歩で吉原へ行くには、浅草・浅草寺を目標にした。上野を抜けて浅草へ出たり、あるいは、日本橋から浅草をめざす。浅草寺に近づくと道が広小路
となりそのまま大川(隅田川)にかかる大川橋(吾妻橋)へつながっている。風雷神門(雷門)の前を通り、大川橋の手前、花川戸を左折し、大川沿いに川の流れと反対に進んで行く。このあたりは当時の二大悪所である吉原と芝居町への入り口だったから、当然人通りも多い。
となりそのまま大川(隅田川)にかかる大川橋(吾妻橋)へつながっている。風雷神門(雷門)の前を通り、大川橋の手前、花川戸を左折し、大川沿いに川の流れと反対に進んで行く。このあたりは当時の二大悪所である吉原と芝居町への入り口だったから、当然人通りも多い。
しばらく行くと左手に曲がる道がある。曲がらずに真っ直ぐ行けば待乳山聖天社と芝居町へ至る。芝居町を抜けていく道順もあるが、吉原をめざすとき、大方のものはここで左へ曲がり、通称・馬道と呼ばれる少し広い道に出る。目の前には浅草寺の本堂や三社権現へ入る門があり、行く手にも寺院が建ち並んでいる。少し先には民家や商家もあって、その前に馬が何頭もつながれており、馬子が客を引いている。
このまままっすぐ歩いていくと、程なく日本堤にぶつかる。これはもともと大川のための土手で、土手の上が道になっているのである。俗に土手八町といわれ、長さが八町(およそ850m)ある。
ここまで来ればあと少しで吉原だ。郊外といえども、吉原へ行く者、帰ってくる者など、武士、町人、人足など様々だが、思ったより人通りがある。程なく吉原の入り口である五十間道が左手に見えてくる。日本堤から五十間道へ下る坂を「衣紋坂」という。これから吉原だと、衣紋をきちんと正したからだといわれている。衣紋坂を下ると、色里には必ずあるという見返り柳がぽつんと立っている。
五十間道は吉原の大門へ続く道だが、直接大門が見えないようにくの字に曲がっている。その左右には数十軒の編笠茶屋が軒を連ねており、顔を見られないように編笠を貸すことからこの名前が生まれたが、実際は初心者のための吉原の案内を仕事にしていた。
これらの茶屋の前を通り過ぎると、目の前には吉原の大門が開いているのである。
なけなしの金を持って吉原に行く町人のほとんどは、以上のような道順をたどって吉原へ辿り着く。しかし吉原へは、徒歩以外にも様々な交通手段を使って通っていた。
【舟で通う】
通人を気取ったり、ちょっと小金を持っている商家の主などは舟をしつらえて吉原へ通った。舟で吉原へ通うのは、馬や駕籠などの乗り物が一時禁止された寛文期(1661~1673)に始まったとされ、元禄期(1688~1704)には川遊びかたがた大いに流行ったという。
吉原通いに用いられた舟は「猪牙舟(ちょきぶね)」と呼ばれた。船尾に櫓がある伝馬船である。この舟は明暦期(1655~1658)頃から吉原通いに使われるようになったが、なぜ猪牙舟と呼ばれたかというと、他の屋形船や屋根舟に比べて速度が速かったためにイノシシのように速いということや、その姿がイノシシの牙に似ていることからといわれる。
『あとを見ぬ 人の乗るゆえ 猪牙という』
という川柳にあるように、さあこれから吉原だと猪突猛進、それしか考えない男たちの乗り物だったのである。
商家の主人が仲間とともに浅草橋や柳橋あたりの船宿で猪牙舟に乗る。そして神田川から大川へ出て、あとは見物しながら上流へと上っていく。舟は山谷堀の入口で止まる。山谷堀にある土手が日本堤である。ここで舟から降り、馬か駕籠を仕立てて吉原へと向かう。山谷堀は、大川と合流する地点は広くなっているが、その先は狭い。舟でさかのぼることはできないのである。
柳橋あたりの船宿から山谷堀までの料金は一艘148文。ただし、この値段は船頭一人の場合である。屋根舟になると300文と、ほぼ倍の値段になる。
【馬で通う】
吉原が浅草田圃に移った初期の頃は、馬で通ってくる客が多かったようだ。まだ、客の中心が武士階級であったためであろう。武士たちが好んだ馬は白い馬で、それに乗る武士も白革の袴に白鞘の刀などを合わせ、伊達に決めて吉原に繰り込んだという。
馬の料金も白馬が一ばん高く、日本橋あたりから吉原まで750文、浅草御門から吉原までは500文といった値段だった(天和元年=1681)。一文30円で計算すると、前者が22,500円、後者が15,000円となる。現在のタクシー料金から見ると少し高すぎる。別の資料(寛文二年=1662)による
と、浅草御門から吉原までが一ばん安い料金で132文とある。一文30円で計算すると3,960円になる。20年の差でずいぶんと値段が違うが、浅草田圃に吉原が移転して営業を開始したのが明暦三年(1657年8月)であり、その年の一月には江戸中が炎に包まれた明暦の大火(振袖火事)が起こって
いる。寛文期は、まだまだ経済的に復興途上であり、吉原も完璧にできあがったとはいいにくく、客も少なかったのではないか。だから料金が安く、二十年たって景気もよくなり、客が増えたため料金が上がったのかもしれない。
と、浅草御門から吉原までが一ばん安い料金で132文とある。一文30円で計算すると3,960円になる。20年の差でずいぶんと値段が違うが、浅草田圃に吉原が移転して営業を開始したのが明暦三年(1657年8月)であり、その年の一月には江戸中が炎に包まれた明暦の大火(振袖火事)が起こって
いる。寛文期は、まだまだ経済的に復興途上であり、吉原も完璧にできあがったとはいいにくく、客も少なかったのではないか。だから料金が安く、二十年たって景気もよくなり、客が増えたため料金が上がったのかもしれない。
だんだん町人に経済力が生まれてくると、馬に乗って通う者も現れた。ただ、町人は江戸市中で許可無く馬に乗ってはいけなかったから、浅草寺裏の馬道なら田圃と同等ということで、そこから馬に乗って吉原に通った。
幕府は馬に乗って吉原へ通うことを禁じたが、なし崩し的に守られなくなり、馬で通うのがよく見掛けられた。しかし、元禄期以降、だんだん馬で通う客が減っていき、江戸の後期になると馬で通う客はほとんど見られなくなった。
【駕籠で通う】
江戸市中の駕籠は、町駕籠あるいは辻駕籠と呼ばれていた。それぞれの町に駕籠屋があって、必要なときにその駕籠屋から駕籠を呼ぶのである。あるいは辻で客待ちをしている駕籠を使うのだ。
ただし、江戸開幕以来、町で駕籠を使えるのは武士のみで、例外として、僧侶と医者に許すという決まりがあった。そして、駕籠に乗ったときは左右の垂れを開けておかなければならなかった。誰が乗っているかわかるようにするため、つまり警備上の理由からである。
もともとこんな決まりがありながら、幕府は何度も町駕籠を禁じた。つまり駕籠に乗る決まりが守られていなかったのである。
駕籠の禁止令は出されては破られ、そしてまた出すということを繰り返しながら、元禄十三年(1700)八月、とうとう幕府は町駕籠を許可し、町人は公然と駕籠に乗ることができるようになった。
ところが、駕籠に乗ってもよいが、吉原通いには使ってはならないという禁令が、翌月の九月に出たのである。悪所へ行く者が駕籠などに乗っていくのは不届きである・・・表面上の理由はこれだったが、実はお尋ね者が吉原へ逃げ込むのを恐れたからという。華やかな繁華街には掟破りの裏組織が存
在する。そこに入ってしまっては、お上も手出しができにくい。そして、それがいつか幕府転覆の企てにつながるかも知れぬ・・・こう考えれば取り締まりやすい状態におくのが当然である。
在する。そこに入ってしまっては、お上も手出しができにくい。そして、それがいつか幕府転覆の企てにつながるかも知れぬ・・・こう考えれば取り締まりやすい状態におくのが当然である。
出しては破られ、また出す・・・駕籠による吉原通い禁止令はいつの間にかうやむやになり、舟とともに駕籠で通う客は後を絶たなかったのである。
料金は、日本橋から吉原で200文。一文30円で計算すると6,000円になる。
6.遊女の一日
一般的な遊女の一日を覗いてみる。
前夜、客を取った遊女は客の朝帰りとともに目覚める。これが卯の刻というから大門の開く午前六時頃である。幕府によって定められた吉原の営業規則では、客は一昼夜以上とどまってはならないので、客は帰り、それを送り出さなくてはならないのである(「居残り左平次」のように「居続け」という場合もある)。
客の着替えを手伝い、羽織などを着せてあげて別れを惜しむ。ここに遊女の手練手管があり、また来てもらえるような素振りをする。遊女として必要不可欠な大事な仕事でもある。
客を送り出した遊女は部屋に戻り、そのまま仮眠を取る。夜中でも客が目を覚ましたら自分も起きるという不文律があったため、客がいる間、遊女は熟睡できなかったのだ。
仮眠は巳の刻頃(午前十時)まで続き、床を離れて風呂に入り、朝食になる。朝食は楼主が振る舞う賄い飯のようなもので。一汁一菜の簡素なものであった。朝食といっても時間的には昼食で、夜見世が始まる前に取る夕食を含めて一日二食が普通だった。
食事の後、部屋の掃除や化粧などをして、未の刻(午後二時)に昼見世に出る。昼間の客の多くは、吉原見物の田舎者などのひやかしで、昼見世は暇な時間帯が続いた。要領のいい遊女は、その時間帯に化粧などをしていた。
昼見世は申の刻(午後四時)にいったん閉める。酉の刻(午後六時)から営業を開始する夜見世まで、遊女たちは、客への手紙を書いたり、仲間と談笑したりという自由な時間を持つことになる。
夜見世が開かれる前に夕食を取り、遊女たちは一斉に夜見世に並ぶ。各見世にも灯がともり、いよいよ吉原の本番を迎える。格子の外を男たちがやってくる。キセルのやり取りなどをしているうちに、遣手から声がかかる。客が決まったのである。客は二階の引付部屋に待っており、そこで対面する。そのまま、部屋なり大部屋なりに行き、客と一杯やりながら話に興ずる。
夜見世が閉まるのが丑の刻(午前二時)で、大引けと呼ばれているが、実際には子の刻(午前零時)に閉める店がほとんどである。この時間になればほとんどの客は登楼してしまい、吉原は静まりかえっている。夜泣き蕎麦屋の声が通りに響くようになるのである。
吉原の夜店に来る客は、そのほとんどが泊まりに来る客であった。帰る客は、吉原以外の岡場所を利用することが多かった。
こうして客と床を共にした遊女は、卯の刻まで床の中にいるのである。単調といえば単調な毎日がこうして年季が明けるまで続いていくのである。
7.遊女の一年
吉原にも独自の年中行事があった。「紋日」(注)というのがそれで、楼主たちの考えた客集めの方策である。必ず客を呼ばなくてはならない年中行事とはいえ、単調な仕事を繰り返す遊女たちにとって、それはそれで楽しみでもあった。
※紋日:遊郭で五節句などの祝日や、毎月の朔日・15日など特に定めてあった日。この日は遊女は休むことが許されず、休むときは客のいない場合でも身揚り(遊女が自分で揚代を負担して休むこと)をしなければならなかった。(「広辞苑」より)
【一月】
正月一日は吉原の休日。この日は楼主がランクに応じて遊女たちに小袖を与えた。そしてお屠蘇に始まり、雑煮が振る舞われる。遊女たちも人並みの元日を過ごすのである。
翌日二日が営業開始日、初見世である。最初の紋日であり、遊女たちは茶屋へ新年の挨拶に出掛ける。吉原の通りという通りは、客よりも挨拶に向かう遊女で埋まったという。
挨拶が済み、見世に戻ってくる頃、新年初の顔合わせとばかりに暮れに約束していた馴染みの客が通ってくる。これを「初買い」といった。
『正月の 二日は遊ぶ はじめかな』
という川柳がある。松の内の間、紋日は続く。
【二月】
二月の年中行事は初午である。初午とは、二月最初の午の日に行われる稲荷神社の祭礼のことで、もともとは五穀豊穣の祈願が主眼だった。それがいつしか商売繁盛につながり、吉原のような客商売にとって初午の祭礼は大切な行事となったのである。
吉原の中には四つの稲荷神社があり、初午の日は遊女や客たちで社は大変に賑わった。
【三月】
三月といえばお花見である。一日から月末まで、吉原・仲の町の真ん中に大きな桜の木を植え並べて垣根をめぐらす。歌舞伎で吉原の場面に登場する舞台装置で、舞台中央に大きな桜の木があるが、あれが仲の町の桜である。通りに面した遊女屋には提灯が飾られ、夜桜見物に客が集まった。そこに花魁道中もあり、これぞ吉原という光景が続くのである。寛政二年(1790)から始まったといわれている。
【四月】
一日は衣替えである。冬の座敷着である綿入れから袷に替わる。
八日は灌仏会だ。これはお釈迦様の誕生日を祝うもので、仏像に甘茶などをかける。
下旬になると仲の町の往来に花菖蒲が植えられる。五月の端午の節句のためのものだが、三月の桜と同様、咲き誇った菖蒲の花を見る客が大勢訪れた。吉原では比較的新しい行事の一つで、安政五年(1858)から始まったという。
【五月】
五日が端午の節句。遊女の部屋には五月人形や菖蒲を飾った。三月三日の雛祭りには雛人形を飾る遊女屋はほとんどなかったが、客が男だけに、端午の節句はきちんと祝ったのである。
この日から袷の着物を単に替え、完全に夏の格好になる。
中旬になると、吉原名物の一つ「甘露梅」の仕込みが始まる。種を抜いた小梅を紫蘇の葉で巻いて砂糖漬けにしたもので、正月、贔屓客に進物として配った。
【六月】
一日は富士山山開きの日で、崇敬の祭礼が各所の富士権現社で行われた。その社にある富士山を形取った小山に登るのである。これは本物の富士登山と同じ御利益があるとされていた。
これらを信仰するのが富士講と呼ばれる集まりで、江戸八百八町に八百八講といわれるほどたくさんあった。吉原にもそれらの人たちが出向き賑わった。
【七月】
一日から仲の町の遊女屋は軒先に灯籠を出す。そして、十五日になると灯籠を新しく作り替えて月末まで出しておく。もともとは玉菊という遊女のために追善供養として新盆に始めたもので、これを玉菊灯籠と呼んだ。
七日は七夕である。笹の葉に短冊をくくりつけるという、おなじみの光景が吉原でも見られた。
十日は浅草の四万六千日で、その客がホオズキなどを片手に吉原に流れ込む。
十二日は仲の町で草市が開かれる。各種の草花が売られていたが、時節柄、お盆に使う草花が中心。早朝から開かれているので、客を送り出した遊女も買いに来た。
十三日は元日と共に年に二回だけの吉原の休業日。遊女たちはのんびりと髪などを洗ったところから、通称・髪洗い日と呼ばれた。
十五日はお盆。玉菊灯籠を新しく作り替えて軒先につるす。
【八月】
一日はいわゆる「八朔」である。八月朔日の略で、この日は古来、農家において豊作を祈願して穀物などを贈答する習慣があり、それが一般化して互いに物を贈り合う日になった。吉原では物のやり取りというより、遊女は白小袖を着ることになっていた。
その起源には諸説あるが、かつてこの日は徳川家康の江戸入りの日。そのため、諸大名、旗本は白帷子を着て登城するのが慣例となっていた。これを真似たものというのが有力である。
一日から八月いっぱい、九郎助稲荷と秋葉権現の祭礼が行われる。この祭礼の名物が「俄」である。俄とは、即興で演じる滑稽な寸劇のことで、笛や鉦、太鼓のお囃子を引き連れ、吉原の芸者衆が通りを練り歩く。
十四日から十六日までは、風流なお月見があった。この月見の時に遊びに来た客は、九月の「後の月見」にも顔を出すという不文律があった。惚れて通うのもいいが、客も大変なのであった。
【九月】
九月は重陽の節句。菊を飾って観賞したり、酒に菊の花びらを浮かべる菊酒を飲む。遊女の衣も、単から袷に替わる。
十二日から十四日までが「後の月見」。先月の月見の宴に訪れた客が再び顔を出す。
【十月】
十月最初の亥の日は「玄猪」といって、餅を作り、無病息災を願って食べる。この餅を「亥の子餅」といい、登楼した客にも配られる。また、この日から見世に大火鉢が出され、綿入れを着始める遊女もいた。
二十日には夷講があった。夷講とは、七福神の一つである恵比須を祀り、知り合いを招いて祝う行事である。恵比須は商売繁盛の神様なので、客商売をする者は皆信仰していた。吉原では、客を招いて一緒に祝うという、一挙両得を狙っていたわけである。
遊女は定紋入りの手ぬぐいを客に配った。「えびす」は、夷、戎、恵比須、恵比寿などと書かれるが、「恵比須」と書かれることが多い。
【十一月】
八日は稲荷祭りが行われ、防災祈願のため、遊女屋ではミカンが庭にまかれた。これを禿たちが拾うのである。この祭りを「火焼(ほたけ)」といった。
この月の酉の日には、浅草・鷲神社(江戸期は長國寺鷲大明神)で酉の市が行われ、熊手を抱えた客が吉原へ押しかけた。そのため、吉原西河岸の裏門を開けて通したという。本来は火事などの緊急時に開かれたが、この日だけは特別に通行できた。
【十二月】
十三日は師走の煤払い、大掃除が行われた。遊女も男たちも総出で妓楼を掃除し、遊女は男たちに定紋入りの手ぬぐいを配る。
二十日、各見世で餅つきが始まり、二十五日には、見世の周囲が片づけられて、正月用の松飾りが施される。吉原の一年もこうして終わるのである。
8.遊女の技
遊女も人気商売である。いかに男たちの気を惹くかを常に考えていた。男たちの人気が高まれば、収入も増えるし、いい格好もできる。
そのための遊女の技が、いわゆる「手練」や「手管」というものだった。
遊女が売れっ子になるための第一条件は、やはり姿形が美しいということである。美人の遊女は何もしなくても客の方が放っておかない。第二は、床上手といわれている。そして、第三が、客あしらいがうまいことだった。この客のあしらい方が手練手管と呼ばれるものである。
例えば、遊女が絶対にしなくてはならなかったのが「きぬぎぬ」と呼ばれる、別れ際の手管である。「きぬぎぬ」は「衣衣」と書いたり「後朝」とも書く。朝、互いに着物を着て別れることである。
床を共にした男を翌朝送り出すとき、また来ようと男に思わせる別れ方を遊女たちは叩き込まれる。いかにも帰るのが惜しいような態度を示したり、後ろから着物を着せるときに抱きついたりして、別れを惜しむ。たとえ、それが演技と分かっていても、遊女にだまされていると分かっていても、男たちはまた通って来ようという気になるのである。このあたりは、昔も今も変わらない。
以下に、遊女の手練手管のいくつかを紹介する。
【口説】
「くぜつ」あるいは「くぜち」とも言う。痴話喧嘩のことである。遊女はなかなか見世に来てくれない客が久しぶりに訪れたとき、口説をした。「どこかで浮気をしてたんでしょ。ずっと待っていたのに・・・」「あなたのことばかり考えていた」などと、客が悦ぶ言葉を並べるのである。
初めての客には、「ただの客とは思えない」「今日会ったのは神様の思し召し」などと、客の心を揺さぶる。
このような月並みなセリフでさえ、時と場合においては効果は絶大だった。遊女はこの数日後までに客に手紙を書くのが常だったという。「あれは本当だったのか」「俺に気があるのかな」と客に思わせるのである。こうして、客は再び通って来るという寸法だ。
『傾城は まことらしげに 嘘をいい』
と川柳にもあるように、遊女たちの「まこと」を「真実」と思う客はいない。それはウソだと客は分かっていた。だが、分かっていながらも信じたくなるところに吉原の魔力があったのである。
【起請文】
「起誓文」あるいは「誓詞」ともいう。遊女が誓いの言葉を文章にしたため確認することである。遊女がいくら口で「お前さんしかいない。年季が明けたら一緒になろうね」と言っても、客はなかなか信用しない。客を信用させるために神に誓い、その証拠として起請文を作るのである。ただし、普通の紙に書
いてはだめで、熊野神社発行の「熊の牛王」という用紙が使われる。これは熊野神社が発行する厄除け護符の一つだが、その裏面には何も書いてなく、そこが起請文として使われる。一枚の起請文を遊女が書いて客に渡すのが一般的だが、同文三枚を作り、互いに一枚ずつ所持し、もう一枚を熊野神社
に奉納するという、手の込んだ方法もあった。
いてはだめで、熊野神社発行の「熊の牛王」という用紙が使われる。これは熊野神社が発行する厄除け護符の一つだが、その裏面には何も書いてなく、そこが起請文として使われる。一枚の起請文を遊女が書いて客に渡すのが一般的だが、同文三枚を作り、互いに一枚ずつ所持し、もう一枚を熊野神社
に奉納するという、手の込んだ方法もあった。
さらに、書くだけでは納得しないという客に対しては、遊女自らが起請文に血判を押して、その信用度を高めた。指を切り、その血で印を付けるというのは、最高の誠意を表す方法だったからである。
【髪切り】
遊女自らの髪を切り、客に渡して誠意を示す方法である。ただし、切るときは遊女が自分で切るのではなく、客に切らせる。客に切らせることによって共犯的な意識を持たせるのである。
切り取られた髪の毛は、いわばその遊女の分身であり、客に持たせることによって、いつでも一緒にいるという気持ちにさせるし、体の一部という意味で誠意も高まるのである。
【爪剥ぎ】
遊女自ら爪を剥ぎ、客に与えて自分の気持ちの強さを表す方法である。髪切りに比べ、爪を剥ぐという行為はかなりの苦痛を伴う。それにより、自分の気持ちはこんなにも強いのだということをアピールしたのである。
しかし、本当に爪を剥いだわけではなかった(中にはいたかもしれないが)。まだ客を取らない妹分の振袖新造の爪を伸ばさせ、長くなったところを切って、いかにも自分の爪を剥いだように見せかけた。
【指切り】
遊女が小指の第一関節から切り、その指を客に与えるというものだ。いうまでもないが、髪切りや爪剥ぎ以上にインパクトが強い。本当に切る場合は、遊女にもそれなりの覚悟がいる。客の方にもそれを受け入れる心構えが必要だった。しかし実際に指を切った遊女は少数で、誠意を示すために指をあ
げるという方法のみが一人歩きし始めると、死体の指を集めたり、本物のように作られた偽物の指が出回ったという。客の方から自分の指を切って差し出す場合もあった。
げるという方法のみが一人歩きし始めると、死体の指を集めたり、本物のように作られた偽物の指が出回ったという。客の方から自分の指を切って差し出す場合もあった。
小指と小指をからめて「指切り、拳万、ウソついたら・・・」という約束方法、いわゆる「指切り」もここからきている。気安く小指と小指をからめているが、本当に小指を切るということは忘れられているようである。寂しいことだ(?)。
【起請彫り】
「文身」ともいう。「○○さま命」というように、客の名前を入れ墨する方法である。入れ墨は一度したら消えないので、生涯あなた一人という意味では強い意思表示になった。
入れ墨の方法は、まず客に二の腕に筆で書かせ、その筆跡を針などで刺しながらたどる。すると墨が皮膚内に入り、入れ墨ができあがる。あるいは、仲間の遊女に彫ってもらうこともあった。
中には偽の入れ墨もあった。ただ墨で書いてもらうというものである。ニカワを混ぜた墨でそれらしく書いてもらうと、簡単には落ちない。それを客にちらりと見せるのである。
本物の入れ墨をしてしまった場合、それを消すことを「火葬」あるいは「腕の灸」という。入れ墨部分に灸をすえて焼き消すのである。本物の彫り師に彫らせたものではないだけに、多少熱い思いをすればきれいに消えた。
『いい施主が ついて命を 火葬にし』
新しい客がついたので、古い客の名前を焼き消したというのを葬式になぞらえて茶化した川柳である。
以上の手練手管の方法を総称して「心中立て」あるいは「心中」という。本来「心中」とは、人に対して心の中で決めた義理を立てることを意味していたが、色里ではそれが手練手管の方法として定着してしまった。
心中立ての行き着く先が「情死」である。好き合った男女が真意を示して二人で死へ旅立つことを、近松門左衛門が心中劇として作り上げ、それ以降、心中が情死を示すことが一般化したのである。
9.遊女の一生
いくら着飾ろうと、江戸中の男たちに愛されようと、しょせん遊女は商売道具でしかなかった(「遊女」を「芸能人」に置き換えれば現代に通じるか)。
休みもほとんどなく、食事も粗末なものが出るだけだ。いいものを食べたければ、懸命に働いて客からお捻りをもらい、そのお金で自前の食べ物を買ったり、見世にあげた客に台の物をとらせご相伴にあずかるしかないのである。
さらに、着飾る着物、帯、化粧品に至るまで、すべて自分で買い整えねばならない。そのために、見世から借金しなければならなかったから、借金は増える一方である。
大名や大商人が贔屓にしてくれる遊女はほんの一握りで、ほとんどの遊女が手練手管を労して客からお金を吸い上げることに精を出した。
『傾城の恋は誠の恋ならず 金もってこいが本のこいなり』
遊女の務めは「苦海十年(苦界とも書く)」と呼ばれ、十八歳から二十七歳くらいまでが吉原で遊女として商売できる期間である。この期間に、身を売った代金、つまり身代金を働いて返さねばならない。これに加えて、前述のように借金が加算されていく仕組みになっており、馬車馬のごとく働かされる。
遊郭の掟や慣例も遊女たちを苦しめた。その掟の見張り役が、遊女上がりの遣手たちである。
遊郭の一ばんの掟は、見世の若い衆と遊女が男女の仲になってはいけないというものだ。見世側とすれば、商品に手をつけられてはその商品が働かなくなる。つまり、若い衆といい仲になると、その遊女が客を取りたがらなくなるのである。
この関係が深くなってしまうと、やがて手に手を取り合って遊郭から逃げ出すということも起こる。いわゆる駆け落ちだが、見世側としては、黙って見逃すわけにはいかない。吉原の地回りなど大勢を使って二人を見つけ出すのである。見つけ出された男はほとんどの場合殺されてしまった。遊女は吉原
へ連れ戻され、凄惨な折檻を受けることになる。殺してしまえば商品としての価値がなくなってしまうが、それでも他の遊女たちへの見せしめの意味もあり、命を絶たれてしまう遊女もいた。
へ連れ戻され、凄惨な折檻を受けることになる。殺してしまえば商品としての価値がなくなってしまうが、それでも他の遊女たちへの見せしめの意味もあり、命を絶たれてしまう遊女もいた。
遊女が苦海から抜け出る方法は三つしかなかった。一つは年季奉公を勤め上げた、いわゆる「年明き」で遊女から足を洗う場合。二つ目は、金のある客に見初められて「身請け」される場合。そして三つ目が死んだ場合。
吉原の年明きは二十八歳なので、この年になった遊女は見世から暇を出される。中には遣手として見世に残る遊女もいたが、多くは吉原の外を望んだ。吉原を出た遊女は、年明きになったら一緒になろうと約束していた男と所帯を持ったり、そのまま吉原以外の色里・岡場所に行く女もいた。
客に身請けされるのが遊女の幸せといわれるが、なかなかそんな客は現れない。特に太夫クラスの上級遊女になれば、身請け金は膨大な額だったのである。もともとの身代金に加え、これから働いて稼ぐであろう金額、これまでの借金、見世や周囲の人間に出す祝い金など、合計すると何百両にもな
る。このような大金をぽんと出すのは、大名や大商人以外は不可能である。
る。このような大金をぽんと出すのは、大名や大商人以外は不可能である。
中級あたりの遊女でも、やはり百両前後はかかったという。ランクが下がれば身請け金も下がるが、宵越しの金は持たねぇと突っ張る江戸っ子には数十両のまとまった金は調達不能だろう。それでも、中にはコツコツお金を貯めて、身請けした町人もいたようである。
死ぬほど辛い苦海・吉原では、実際に死んだ遊女の数は知れない。粗末な食事で馬車馬のように働かせ、体力は消耗する一方だが、さらに病気が追い打ちをかけた。遊女たちが一ばん恐れた病気が梅毒であった。
梅毒はもともと西インド諸島の風土病で、コロンブスが西インド諸島に到達し、スペインに帰国した際、その船員たちがヨーロッパに運んだといわれている。シャルル八世のナポリ攻撃以来ヨーロッパから世界に広がり、日本にも十六世紀の半ば南蛮船の来航によって上陸した。ちなみに日本の文献には
それよりも前、1512年に「梅毒」という言葉が登場している。
それよりも前、1512年に「梅毒」という言葉が登場している。
当時梅毒は、「かさ」などと呼ばれていた。感染すると感染部におできのようなかたまりができ、これがかさぶたのようになるからである。この「かさ」が潰れると、痛みを伴うがしばらくすると治ってしまう。実際は一次症状が収まって潜伏しているだけであるが、当時の医学知識ではこれで治ったと思って
いた(治ってしまう場合もあったが)。
いた(治ってしまう場合もあったが)。
一度「かさ」にかかって治った(と思っている)遊女は、二度と梅毒にかからないとされ、客の方でも病気のない遊女として認知された。見世からも一人前の遊女として扱われ、遣手は客にどんどん勧めた。おまけに病気が潜伏している影響か、妊娠しにくい身体になっているから、見世としては大変重宝した。こうして、梅毒はどんどん広がっていったのである。客の方でも、梅毒にかかることは一種のステータスで、遊びを極めているという目で見られた。
何年か後、再び症状が現れると、今度は皮膚にゴム状の腫れ物が出て、その部分の肉が落ちる。鼻が落ちるといわれる梅毒の症状はこの時期だ。
やがて神経系が冒され、死に至る。
やがて神経系が冒され、死に至る。
こういう症状が出ると遊女としての価値はなくなり、吉原を追い出されたり、生きたまま投げ込み寺へ捨てられたという。悲惨な結末が遊女を待っていたのである。
梅毒とともに遊女を悩ませたのが妊娠だった。妊娠は遊女の恥とされ、さまざまな避妊法を用いたが、当時の知識では妊娠は避けられない出来事だ
った。
った。
当然見世側とすれば中絶させたが、この手術も原始的なもので危険極まりないものだった。中条流というのが堕胎専門医師の看板で、中絶に失敗して命を落とす遊女も多かったという。
堕胎できずに子供を産んでしまった場合もあった。この場合は、見世の子供として育てられ、女の子なら遊女の道へ、男の子なら見世の若い衆として将来は決められた。まさに、吉原生まれ吉原育ちの遊女もいたわけである。
10.その他の遊郭